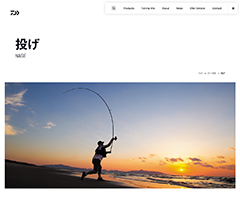今年は、ジャパンフィッシングショー2015(以下横浜Fショー)がパシフィコ横浜で1月30日(金)~2月1日(日)に開催。フィッシングショーOSAKA2015(以下大阪Fショー)は翌週の2月7日(土)~8日(日)にインテックス大阪で開催されました。
今年の超目玉商品といえば、このトーナメントマスタライズキス SMT。

この竿を見に来る熱いキャスター諸兄がたくさん来場されました。
講演では、横浜Fショーでは高橋テスターが、
大阪Fショーでは松尾テスターが『テクノジーが変える競技の世界』と題してトーナメンターならではの視点で熱く語って頂きました。

トーナメントマスタライズキス SMT以外にも、キャスティズムやプライムキャスターにも拘りを持ったアイテムを追加。
振出投竿では青サーフこと「スカイサーフT」が生まれ変わりました。

超高密度SVFカーボンを採用し強靭性を増した本格的振出投げ竿として、三脚を用いての複数使用(カレイ/大型キス/マダイなど大物系)のキャスターたちは、真剣に号数の確認と調子を確かめていました。
さらに、三代目赤サーフの「トーナメントサーフT」には、昨年から多くのキャスターから切望されていた「25号」に405と425に追加。よりライト趣向の大物派キャスターの腕の延長となる、しなやかな仕様を追加しました。
投げ専スピニングリールはパワーサーフQDがマグシールドを搭載して12年ぶりのモデルチェンジ。前作とのスプールの互換性もあり、ますます利便性が良くなりました。

それ以外にもグランドサーフ35やキャスティズム25QDに追加があり、ますます投げ専リールが充実。
Fショーならではといえば、カタログにも掲載のない特別製品の展示。いわゆる参考出品。

フロートシンカーのタングステンバージョン。タングステンの先端部が細くなっており飛距離が出そうなフォルムが特徴的。
今年も投げに対する熱い想いが十分に伝えたフィッシングショーでした。