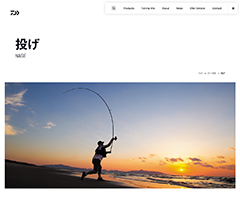文・写真・/中本嗣通 なかもとつぐみち 1958年大阪府生まれ DAIWAフィールドテスター 投げ釣り倶楽部大阪会長
日ごとに暖かくなっていく陽差しに誘われて、今年の2月にリリースされたNEWロッドである
を携えて早春の瀬戸内海へと釣行してきました。
人間様がいくら「暖かい…」と感じていてもひと足遅れとなる海底の水温はいまだ冬ですから、狙うターゲットは低水温に強いアイナメやカサゴといった”根魚”となります。
根魚狙いはポイントによって根掛かりとの戦いとなるキツイ場面も多いのだが、それも春が近づいて身に脂が乗りだしてメッチャ美味しくなる根魚の「甘辛の煮付け」を味わうためならば、多少の苦労なんぞは惜しみまへんで(笑)。
そして、今回の釣行では
をジックリと使い比べてそのポテンシャルに差を見つけてやろうという、もう一つの目論見もありまっからネ♪
夜半過ぎから釣り場に入ると、まずは赤サーフのタイプRとタイプWの穂先にケミカルライトを装着し、イワイソメを刺した1本バリ仕掛けをシモリがあるエリアへキャストして「サーフスタンド750」に並べます。
春の根魚は意外と暗い時間帯に活性を上げるケースが多く、寒さに耐えながらの夜釣りで攻めるパターンもめずらしくありません。
当日も深夜の時間帯はアタリが遠い状況が続きますが、夜明け前に満潮から引きへと潮が動き始めたタイミングに不意に時合いが訪れます。まるで待ちかまえていたかの様に15~21㌢のカサゴが5匹と25~28㌢の中型アイナメ3匹が次々と魚信を送ってくれましたが、明るくなるとポイントは無限のイソベラ&クサフグ地獄へと突入。
その後は投げても、投げても、投げ続けても仕掛けが着底すると同時にイソベラとフグによってアッという間に空バリにされる虚しさから、早々と納竿を決めて帰路に就いたのでありました。
さてさて、外道地獄に陥った虚しい時間帯を利用して予定どおり”W”と”R”を同時に使用して、そのポテンシャルの差を探ってみました。
まず、Rのデザイン面では元竿部分やシッカリと握りこめることでキャストにアドバンテージを発揮する
「バーミンググリップシート」
の締め込みで映える「カラークロス」と、細部にまで金色を配したカラーリングが目を引き、前作Wをよりゴージジャスにした印象を受けます。
そんなRを実釣に使用しての第一印象といえば、前モデルのWと比べて
「振り抜けの良さ」
を感じられたこと。
これは速いスイングスピードによって曲げた穂先に残る負荷が、絶妙のタイミングで反発をみせて射出することから得られるフィーリングに他ならないと思います。
また、当日のような底根の荒いポイントからハリに掛けた魚を一気に離すための大きな合わせや、障害物をクリアするためにイチ早く掛けた魚を浮かす強引な巻き取りを敢行したケースにおいて、Rの「起こすパワー」がWよりも優れているように感じられました。
…かといって、それはカンカンの硬い先調子の投げロッドがみせる圧倒的なハイパワーとは異なる
「しつこい粘り」
に通じる ”したたかな反発のパワー”だといえます。
そして、僕が「釣りを楽しむために欠かせない釣り竿の要素」と考えるのが、ハリに掛った魚の生命感を増幅して
伝えてくれる”竿の曲がり”です。それだけにNEW赤サーフのRは「しなやかな調子」で美しい曲がりを作りキャスターへ魚の動きをシッカリと伝わるように設計されていることは好感を持てましたで。
もちろん、RとWに感じたこれらの性能差はごく小さなレベル。
これらの差はRで新たに採用された新素材の
「SVFナノプラス」
や新機構の
「Ⅴジョイントα」
などが作りだした数々の小さな差だと考えられますが、それらのRで寄り集まった”小さな差”の相乗効果によって『トーナメントサーフT』の性能がより進化を遂げたことを、今回の釣行で充分に認識することができました。
なお、コスパもダイワ振出投げ竿のフラッグシップモデルでありながら僕が得意とする「置き竿釣法」で必要な複数本を揃えるにも納得できる抑えた価格設定になっていますから、この面でも開発スタッフの苦労が見え隠れしてまんな…。
てなことで、僕が繰り広げる今シーズンの投げ釣りシーンにおいて、この安定した実力が魅力的な
が大活躍をするエモーショナルな展開が期待できそうでっせ ❤